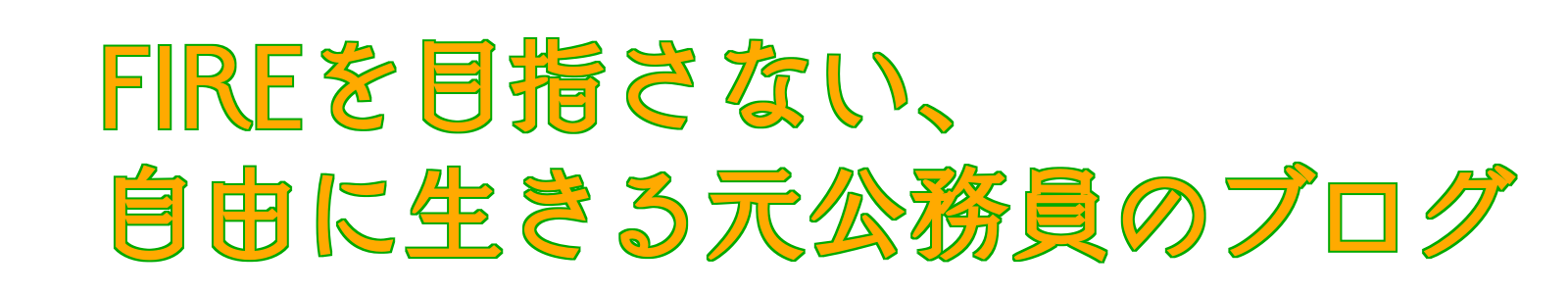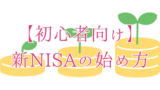「公務員は副業NGだけど、投資もダメなの?」
「懲戒処分になったらどうしよう…」
と不安で一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
※2026年1月時点では国家公務員の副業は解禁されていませんが、2026年4月~見直されるとのことです。(人事院の報道資料より)
結論から言うと、公務員が資産運用として投資を行うことは、原則として認められています。
この記事では、元公務員の私が実体験と公式ルールをふまえ、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 公務員の投資に関する規制
- 公務員の特性を活かせる資産形成の考え方
- 初心者が知っておくべきNISAのメリットとリスク
この記事を読んでいただくことで、投資に対する漠然とした不安が解消され、ご自身の将来に向けた一歩を堂々と踏み出せるようになるはずです。
公務員は投資をやってもOK?|規則の確認
人事院の一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)には、このように記載してあります。
Q.株式の所有や売買は、兼業規制との関係で問題になりますか。
A.単に資産運用の一環として株式を所有したり、売買することは兼業規制に抵触するものではありません。
(ただし、府省によっては、インサイダー取引の防止等の観点から、内規等で株取引等を制限している場合もあります。また、本省審議官級以上の職員については、国家公務員倫理法に基づく株取引等の報告が必要となります。)
なお、株式所有については、一定の場合に報告等が必要になる場合があります(下記参照)が、保有株式が発行済株式総数の3分の1以下である場合や、所属府省と当該企業との間に職務上の関係が一切ない場合には、下記の報告等は必要ありません。
<報告が必要な場合とその際の対応>
①発行済株式総数の3分の1(特例有限会社は4分の1)を超える株式を所有し、かつ、
②その会社が職員の所属する府省の行政上の権限や行政指導の対象となっている場合等は、株式の所有状況について人事担当部局へ報告する必要があります。報告の結果、職務遂行上適当でないと判断された場合には、・株式を一部売却・譲渡する・株式を一部議決権のない株式とする・共有で権利行使者を別に指定するなどして職員が議決権を事実上有さず、かつ、議決権行使の指図も行 わないようにする等の措置をとることで対応することができます。
これを要約すると、問題となるケースは次のとおりです。
一部府省では内規で株取引を制限する場合がある。
審議官級以上の職員は株取引の報告義務あり。
株式保有に関しては、
発行済株式総数の3分の1(特例有限会社は4分の1)超を所有し、
その会社が所属府省の行政権限の対象である場合
つまり、
・内規で株取引を制限されていない
・審議官級以上でない
・行済株式総数の3分の1(特例有限会社は4分の1)超を所有していない、かつその会社が所属府省の行政権限の対象でない
であれば、問題ないようです。
なぜ公務員にNISA(つみたて投資枠)が活用しやすいのか?
公務員とNISA(特につみたて投資枠)の相性が良いと言われる理由は、制度の特徴と公務員の職業特性がマッチしやすいからです。
- 長期・安定収入との相性:
毎月一定額をコツコツ積み立てる手法は、安定した給与収入がある公務員にとって取り組みやすい方法です。 - 税制上のメリット:
通常、投資利益には約20%の税金がかかりますが、NISAなら非課税となります。 - 選び抜かれた商品:
金融庁が「長期・積立・分散」に適したと判断した投資信託が対象のため、初心者でも商品選びのハードルが下がります。
NISA(つみたて投資枠)で知っておくべき注意点
メリットだけでなく、リスクや注意点を正しく理解することが大切です。
- 元本保証がない:
預金とは異なり、価格変動によって購入金額を下回る(元本割れ)可能性があります。 - 損益通算ができない:
NISA口座で損失が出ても、他の口座の利益と相殺して税金を安くすることはできません。 - 長期運用が前提:
短期間では利益が出にくい、あるいはマイナスになることもあるため、数十年単位の長い目線で取り組むことが推奨されます。
まとめ:将来の不安に備えた一歩を
公務員の投資について解説してきました。
- 原則として、資産運用としての投資は問題ありません(※ただし、職種や役職、所属する組織の内規によって制限の対象となる可能性がございます。トラブルを避けるためにも、事前に最新の規定をご確認ください)
- 安定した収入を活かせる「NISA(つみたて投資枠)」は有力な選択肢の一つ
- ただし元本保証はないため、リスクを理解した上で少額から始めるのがコツ
「投資=ギャンブル」ではなく、「将来の自分を守るための備え」として、まずは少額から経験を積んでみてはいかがでしょうか。
各証券会社で取り扱う金融商品(株式、投資信託、NISA等)への投資には、価格の変動等により元本を割り込む(損をする)リスクがあります。また、商品ごとに所定の手数料等がかかる場合があります。
当サイトの情報は個人の見解・体験をもとに作成しており、特定の金融商品の取得を勧誘するものではありません。投資に関する最終決定は、公式サイトに掲載されている「契約締結前交付書面」等をよく読み、ご自身の判断と責任で行ってください。
掲載情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報については、必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。