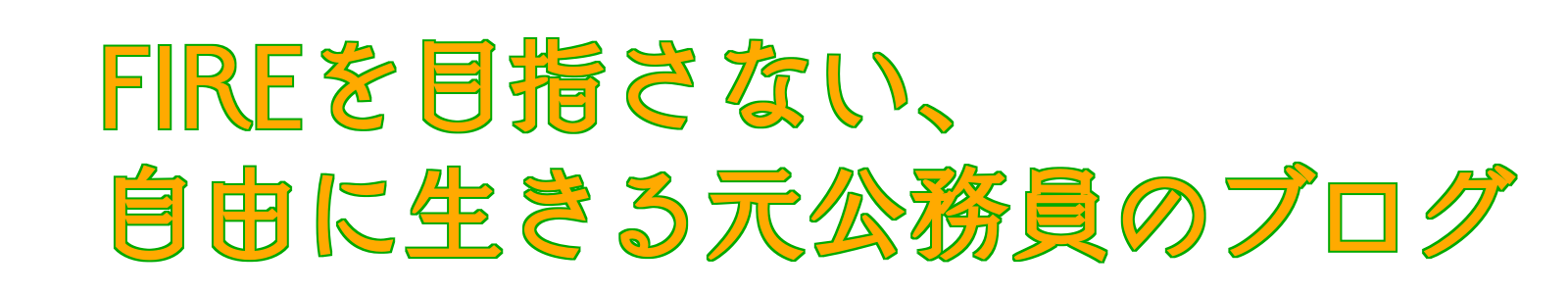iDeCo(イデコ)は「将来の年金を自分でつくる」ための制度です。
でも「仕組みが複雑で何から始めればいいかわからない…」と感じる方も多いはず。
この記事では、初心者向けにiDeCoのメリット・デメリットから、金融機関の選び方、始め方までわかりやすく解説します。
- iDeCo(イデコ)とは何か
- iDeCoの節税メリット
- iDeCoのデメリットや注意点
- 金融機関の選び方
- iDeCoを始めるまでの流れ
iDeCo(イデコ)とは
iDeCo(イデコ)は、「個人型確定拠出年金」の略で、 自分で積み立てて運用し、60歳以降に年金や一時金として受け取る自分年金です。
特徴は次の通りです。
加入できる人
基本的に20歳以上65歳未満のほとんどの方。(※一定の条件があります。詳細はiDeCo公式サイト(国民年金基金連合会が運営しています)を確認ください。)
掛金を自分で決める
毎月いくら積み立てるか、自分で設定できます。
ただし、職業によって掛金上限額が異なります。(※詳細は、iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会が運営しています)を確認ください。)
運用先を自分で選ぶ
投資信託・定期預金など、運用商品を自分で選べます。
節税になる
- 掛金が「全額所得控除」 → 所得税・住民税が軽くなる
- 運用益も非課税
- 受取時も一時金なら「退職所得控除」、年金形式なら「公的年金等控除」が適用
原則60歳まで引き出せない
老後資金専用の制度なので、途中でお金を使えません。
iDeCo(イデコ)のメリット
主なメリットは次の3点です。
運用益が非課税
株や投資信託で利益が出ると通常20.315%の税金がかかりますが、iDeCoなら運用益は非課税です。
掛金が「全額所得控除」される
所得控除とは?
所得控除とは、課税対象となる所得(=税金の計算のもとになるお金)から、一定の金額を差し引ける仕組みです。
差し引かれた分だけ、所得税や住民税が少なくなります。
iDeCoの掛金は「全額控除」
iDeCoの場合、毎月支払う掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になります。
つまり、月々1円でも2万円でも、払った金額はそのまま課税所得から引くことができます。控除されることで、所得税・住民税の両方が軽くなります。
税金がどれくらい減るかの例
仮に年収500万円の会社員が月2万円をiDeCoに拠出した場合(年間24万円):
※ここでは分かりやすくするため、所得税率を20%、住民税率を10%と仮定します。
控除効果:
- 所得税:24万円 × 20% = 4.8万円減
- 住民税:24万円 × 10% = 2.4万円減
合計で年間7.2万円が節税効果の目安となります。
※実際の課税所得は「年収」から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などを差し引いた金額で計算されます。そのため、個々の状況によって適用される税率や節税額が変わります。
受け取る時も控除が受けられる
iDeCoは年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。
※控除とは、税金を計算する際に「引いていい金額」のことです。 結果、本来かかるはずの税金を抑えることができます。
iDeCoのデメリット・注意点
iDeCoにはメリットが多い一方で、注意すべき点もあります。主なデメリットは次の3つです。
原則60歳まで引き出せない
iDeCoの最大のデメリットとして、原則として60歳まで資金を引き出せない点が挙げられます。
万が一のときでも引き出せないのは、精神的に負担に感じるかもしれません。
預金などで日常生活に必要なお金を十分に確保しておくことで、安心して運用に取り組めると思います。
元本保証なし
iDeCoで投資信託を運用する場合、預金とは異なり元本保証はありません。相場変動により、受取額が投資した総額を下回る「元本割れ」の可能性があります。
- 投資に絶対はありません。利益が出ることもあれば損をすることもありますが、そのすべてが自分の運用実績となります。
- 「長期・積立・分散」投資を行うことで、一時的な下落リスクを軽減し、着実に資産を増やせる可能性が高まります。
- リスクを避けたい場合は、定期預金などの「元本確保型」の商品を選ぶことも可能です(ただし、利回りは低めになります)。
手数料がかかる
iDeCoでは、運用にあたって手数料が発生します。
○加入時・移換時(口座開設時、または企業型確定拠出年金からの移換時※初回のみ)
| 支払先 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 2,829円 |
○運用中(毎月かかる)
| 支払先 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 105円 ※新たな掛金(毎月の積立)を行わず、過去に積み立てた資産だけを運用している人は不要 |
| 信託銀行 | 66円 |
| 運営管理手数料 | 金融機関によって異なる。 ネット証券は0円が多い。 |
○運用商品にかかる手数料
| 投資信託の場合:信託報酬など | 年0.05%〜2%程度が多い |
○受取時(1回につき)
| 支払先 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 信託銀行 | 440円が多い |
金融機関選びで節約できるのは「運営管理手数料」
- iDeCoでは、運営管理手数料が金融機関ごとに異なります。
- 運営管理手数料は金融機関によって差があるため、0円のところを選ぶと節約できます
詳細な比較はこちらの記事でチェック
▶手数料が安いのはどこ?【iDeCo(イデコ)】おすすめ金融機関まとめ
毎月の手数料の目安
- 国民年金基金連合会+信託銀行への手数料は、どの金融機関でも毎月171円かかります。
- これに加えて、運用する投資信託の信託報酬がかかります。
- 運営管理手数料が無料の金融機関を選ぶと、実質「毎月171円+信託報酬」で運用できます。
手数料は少額でも、長期運用だと差が大きい
毎月数百円の手数料の差でも、積立期間が長くなると数万円〜十数万円程度の差になることもあります。※iDeCoは数十年の長期運用が基本です。
iDeCoを始める流れ
「手続きが難しそう…」と感じるiDeCoですが、それぞれの金融機関でおおよその流れは共通しており、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。
- 金融機関を選ぶ
- 口座開設の申し込み
- 掛金額・運用商品を設定
- 自動積立開始
金融機関ごとに手数料や商品ラインナップ・独自のサービス・サポートなどが異なるため、自分に合った選択が重要です。
まとめ
iDeCoは「節税」と「将来の資産形成」を同時に実現可能な制度です。
- 長期運用+自動積立で初心者でも資産形成できる可能性がある
- 手数料が安く、自分に合うサービスやサポートが受けられる金融機関選びが重要
- 原則60歳まで引き出せない点には注意
少額からでもコツコツ積み立てることで、将来の自分に大きな資産を残せる可能性があります。
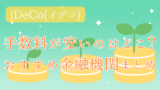
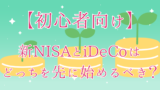
各証券会社で取り扱う金融商品(株式、投資信託、NISA等)への投資には、価格の変動等により元本を割り込む(損をする)リスクがあります。また、商品ごとに所定の手数料等がかかる場合があります。
当サイトの情報は個人の見解・体験をもとに作成しており、特定の金融商品の取得を勧誘するものではありません。投資に関する最終決定は、公式サイトに掲載されている「契約締結前交付書面」等をよく読み、ご自身の判断と責任で行ってください。
掲載情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報については、必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。